【ゼロから分かる】映え確定の芸術作品フンデルトヴァッサースポットの歩き方

なんかカラフルでおもしれーアパート。
予備知識なしで訪れれば、多くの人がだいたいそんな感じの印象を持つであろうフンデルトヴァッサーハウス。
ウィーン観光では王宮やら博物館やらカフェやらで行くとこ見るとこたくさんあって大忙しが常ですが、ウィーンでしか味わえない芸術スポットの一つとしてしばしばその名を挙げられます。
決して煌びやかな内装なんかが見られるわけではないため、多くの観光ガイドでもシェーンブルンなどの一軍スポットたちと肩を並べられているとは言えない知名度です。
しかし他の芸術家の作品と違い、敷居の高い「芸術」というジャンルに置いて誰でも直感的にそのセンスを堪能できるという点では非常におすすめの場所と言えるはず。
今回はこのフンデルトヴァッサーを堪能できる観光スポットを予備知識なしのゼロからでも分かるようご紹介します。
ちなみにインスタ映えを狙う方にもぜひ足を運んでほしい映えスポットです。
フンデルトヴァッサーって誰?
フンデルトヴァッサーと呼ばれていますが、これ実は本名ではありません。
本名はFriedrich Stowasser(フリードリヒ・シュトヴァッサー / 1928 – 2000)、芸術家としての名前がFriedensreich Hundertwasser Regentag Dunkelbunt(フリーデンスライヒ・フンデルトヴァッサー・レーゲンターク・ドゥンケルブント)。
略してHundertwasser(フンデルトワッサー)と呼ばれるオーストリアを代表する芸術家であり建築家、そして思想家の一人です。
ドイツ語でFriedが平和、reichがリッチ、Hundertが百、wasserが水、Regentagが雨の日、Dunkelが黒、Buntがカラフル、と芸名からして何やら凄い信念を感じさせますね。
フンデルトヴァッサーはなぜ有名な人なの?
フンデルトヴァッサーハウスを訪れる前にぜひ知っておきたいのが彼の独自性。
これを知っているか否かで実際にその作品を目にした際の印象は全く異なって見えるほどです。
まずフンデルトヴァッサーが世界的に有名になった理由は、単に「奇抜だから」ではなく、芸術・建築・思想の3つの面が強く結びついていたからと言われています。
20世紀当時の美術界の中で、抽象画にも関わらず自然や人間味を強く感じる独自のスタイルを築き、鮮やかな色彩や渦巻き・不規則な形が一目で「あ、これフンデルトヴァッサーだ」とわかる強烈な個性を持っていたことが、まず芸術家として彼の独自性を確立させました。
特に渦巻きのモチーフは彼の絵画の中心的なテーマとされており、自然界の形を象徴し、生命や成長の循環を表現しているそう。
その上で絵画や版画だけでなく、ポスター、切手、旗、デザイン作品にも広く展開し、多くの人の目に触れたことも有名になった一つの要因です。
そしてフンデルトヴァッサーは大の「直線嫌い」で、かつ自然との共生という思想を実際の建築で具現化し、屋上緑化・リサイクル建築・環境共生住宅など今日のエコ建築の先駆者として、建築家としての革新性も持ち合わせていました。
「直線は非人間的」「木の借家人(窓から木を育てる)」など、ユニークなメッセージを発信し、環境保護・自然回帰・個人の自由と創造性の尊重を早い時期から訴え、社会に影響を与えたことで思想家としても知られるようになりました。
一言で言えば「芸術 × 建築 × エコ思想」を結びつけ、20世紀を代表するオンリーワンのアーティストになったというわけです。
日本の建築にも携わっている
フンデルトヴァッサーの制作物はオーストリア国内だけではなく、ドイツ、アメリカ、スイス、ニュージーランド、イスラエルと他国にも作例があります。
特に、日本でも建築に携わっていることは知らない方も多いかもしれませんね。
TBS東京21世紀カウントダウン時計、キッズプラザ大阪のこどもの街、大阪市環境局舞洲工場、大阪市舞洲スラッジセンターと、フンデルトヴァッサーは1990年以降、日本の著名な建築もいくつか制作しているんです。
フンデルトヴァッサーを堪能できるウィーン市内のスポットは一つじゃない
ここまででおおよそフンデルトヴァッサーの作品がどんなものかお分かりいただけたかと思います。
そしてウィーンでは、このフンデルトヴァッサーが手掛けた建物や博物館があちらこちらにあるんです。
Hundertwasserhaus
https://hundertwasserhaus.info/
住所
Kegelgasse 36-38, A-1030 Wien
営業時間(インフォメーションセンター)
3月1日~4月30日 9:00~17:00
5月1日~11月2日 9:00~19:00
11月3日~1月8日 9:00~17:00
1月9日~2月末 休業
入場料
無料(内覧は不可)
今も現役のフンデルトヴァッサー作品
正式名称はHundertwasser-Krawina Haus。
フンデルトヴァッサーと言えばここ「フンデルトヴァッサーハウス」。
彼のデザインが全開の、カラフルで手書きの線で区切られたような集合住宅です。
小道に木漏れ日をもたらす木々もかなりチルいアクセントになっているのが分かると思います。
なによりも驚きなのはここに実際に人が住んでいるという点。
言ってみれば私たちは勝手に人の家をパシャパシャ写真を撮っているわけですが、もちろん住んでいる人たちもそれは事前に知らされており、逆にこのアパートに住んでいることが一つのステータスになっているほどです。
とは言え許可なく中に入ることは出来ませんので注意が必要ですし、節度ある撮影が大事であることは言うまでもありませんね。
日本で言う一階の一部はインフォメーションセンターとなっており、限定のガイドブックやポストカードが販売されています。
フォトスポットとしての散策になるので、時間的には5分~10分程度で満喫できると思います。
ちなみにKrawinaというのはオーストリアの建築家Josef Krawina(ヨーゼフ・クラヴィナ)の名前です。
ウィーン市の市営住宅プロジェクトにおいて、フンデルトヴァッサーとコラボし、フンデルトヴァッサーはデザインを、クラヴィナがそれを建築的に成立させる役割を担い、1983~1985年に建てられた経緯があります。
実際の所、建築の実務面ではクラヴィナの貢献も大きかったため、ウィーン市や一部の公式資料では「Hundertwasser-Krawina-Haus」という表記が用いられ、法的に「共同作品」と認定されているわけです。
ここに住めるの?
住めます。
市営住宅なのでもちろん条件はありますが、家賃も比較的低めと言われています。
ただ、なによりもここを自ら出ていく人があまりいない様で、入居待ちは非常に長いそう…。
上述の通り中を見ることは叶いませんが、各部屋内は割と控えめなデザインだそうで、ちゃんと直線もあるみたいです。
ただ、バスルームのタイルが不規則な配置だったり、窓枠が一つ一つ異なるなど、細部において従来のアパートでは味わえない作りなようです。
Terrassencafé im Hundertwasserhaus
https://www.hundertwasserterrassencafe.at/
住所
Kegelgasse 34-38, A-1030 Wien
フンデルトヴァッサーハウスの少し脇にある階段を上がるとテラス席のある小さなカフェもあります。
特段変わったメニューは無く、また後述のショッピングエリアにもカフェはあるので優先度は高くありませんが、冬限定でプンシュやグリューワインが注文できることは覚えておいて損は無いかもしれません。
Hundertwasser Village
https://www.hundertwasser-village.com/
住所
Kegelgasse 37/39, A-1030 Wien
営業時間
月~日 9:00~19:00
入場料
無料
フンデルトヴァッサーの小さなテーマパーク
フンデルトヴァッサーハウスのちょうど向かいにある小さ目なショッピングエリア「フンデルトヴァッサー・ヴィレッジ」。
以前タイヤ修理工場として利用されていた建物を、1990年から1991年にかけてフンデルトヴァッサーの構想と構想に基づき、内外装ともに建設された場所です。
外からしか見られないフンデルトヴァッサーハウスに対し、こちらは中も自由に散策出来ます。
可愛らしい、というかフンデルトヴァッサーらしいお土産屋やカフェがひしめいており、床も壁も天井もトイレもフンデルトヴァッサー特有のカラフルで曲線的な内装に仕立て上げられています。
マグカップ、絵画の複製、文房具、ミニチュア模型やデザイン書籍などフンデルトヴァッサー関連グッズを買うも良し、カラフルで独特な空間でお茶や軽食を楽しむも良し、フンデルトヴァッサー風トイレを堪能するも良しのおすすめスポットです。
ちょっとしたギャラリーや模型も展示されているので、気軽にフンデルトヴァッサーの思想に触れることもできます。
ちなみにモーツァルトクーゲルなどのウィーンお土産雑貨なども売っていますが、これらはここでなくても買える上ちょっぴり高めなので、無理にここで買う必要はありません。
一通り散策するだけなら20分~30分程度で一周できると思います。
Kunst Haus Wien – Museum Hundertwasser
https://www.kunsthauswien.com/
住所
Untere Weissgerberstrasse 13, A-1030 Wien
地下鉄で来るならU1「Schwedenplatz」「Praterstern」、U2「Praterstern」、U3「Landstraße」「Rochusgasse」、U4「Landstraße」「Schwedenplatz」辺りが最寄りですが、そこから徒歩10分と少し遠め。
前述のフンデルトヴァッサーハウスやヴィレッジからも5~10分程度の徒歩で来ることが出来るので、散策がてらこちらも訪れるのも良いかと思います。
あまり歩きたくない方はトラム1・Oで「Radetzkyplatz」で降りれば徒歩2分程で着きます。
営業時間
月~日 10:00~18:00(チケット売り場は17:30まで)
入場料
一般 16,00ユーロ
割引 13,00ユーロ
65歳以上 13,00ユーロ
26歳未満の学生 7,00ユーロ
19歳未満の子供 7,00ユーロ
10歳未満の子供 無料
ファミリーチケット 27,00ユーロ(子供1名~4名、大人2名)
年間パスポート 29,00ユーロ
割引価格は、障がいのある方、徴兵対象者、公務員、無職の方、Ö1クラブ、ÖAMTC、ウィーンシティカード、10名以上の団体が対象。
ICOM会員の方や「Hunger for Art and Culture Card」を持っている場合は無料になります。
年パスは一般料金で計算するなら2回訪れれば元を取れる計算になるので、企画展もやっていることを考えるとウィーンに住んでいる方にも割とおすすめです。
オーディオガイド
ガイドのみ 4,00ユーロ
貸出端末込み 5,00ユーロ
言語はドイツ語、英語、フランス語のみ。
スマホのブラウザから利用することが出来ます。
フンデルトヴァッサーを知るならここ
1991年4月9日に開館した、フンデルトヴァッサーの作品を体系的に展示している公式美術館。
前述のアパートやヴィレッジが観光よりの場所であることに対して、こちらは彼の絵画、版画、建築模型、デザイン、思想など芸術面をまとめて見られる唯一の場所です。
もともと家具工場をフンデルトヴァッサーが改装したもので、他と同じく彼らしい曲線やカラフルな装飾が施されています。
建物は4階建てで、うち2フロアがフンデルトヴァッサーの常設展、2フロアが企画展となっており、じっくり見るなら1.5~2時間、駆け足なら1時間程度で一周できる規模感です。
施設内のショップでは、フンデルトヴァッサー作品に関連したアートプリント、ポスター、スカーフなど、アーティスティックよりなギフトが多い印象です。
その他、現在開催中の展覧会に関する出版物やカタログなども置いてあります。
また、ロッカーも利用できることは覚えておいて損はないです。
Café Friedlich
営業時間
月~日 10:00~18:00
メニューはちょっぴり高めですが店内の雰囲気も料理も映えについては相当レベルが高い施設内のカフェ。
インスタ勢ならそこいらの有名店で食べるよりも断然おすすめです。
メニューの種類もぶっちゃけ字ずら読んだだけでは全くピンとこないお洒落なものが多いので、ガッツリ腹を満たしたい方は値段からある程度ボリュームを察するようにした方が良いです。(シュニッツェルもあります)
ただ時間帯によってはかなり混んでいることもあるので、ある程度時間にゆとりを持って訪れた方が良いかもしれません。
オーストリアにちりばめられたフンデルトヴァッサーのデザイン
フンデルトヴァッサーについて深堀している施設はこれらがメインですが、これまでご紹介してきた通りフンデルトヴァッサーは多くの建築作品を国内外に残しています。
ウィーンのシュピッテラウ焼却場やベルンバッハのフンデルトヴァッサー教会、ツェル・アム・ゼーの噴水、温泉ホテルログナー・バート・ブルマウなどなどオーストリア国内を散策していてもふとしたきっかけで見かける特徴的なデザイン。
精巧な絵画や彫刻などとは異なり、彼の作品は一瞬で見分けがつき親近感も湧きやすい、いわゆる私のような芸術素人でもとっつきやすいことが魅力です。
金に輝く荘厳なインパクトはありませんが、気軽に触れられる芸術の一つなので、ウィーンを訪れた際にはぜひ足を運んでみて下さい。

コレクター魂が熱くなる!ユーロの硬貨について

知っておいて損はない!オーストリアのマナーについて

【Vienna City Card】本当に元取れる?ウィーンの割引特典付き交通機関チケット

オーストリアですぐに使える3分ドイツ語

ちゃんと届く?日本からオーストリアに郵便を送る方法

【チケットの選び方】ゼロから分かるシェーンブルン観光【地図あり】

【ばらまき用】オーストリアのスーパーで買えるお土産用お菓子ブランド

オーストリアの郵便局と国内・日本へ荷物を送る方法

どうやって美味しく食べる?ドイツ・オーストリアのザワークラウト

【初めてでも簡単】ウィーン市内の交通チケットの種類と買う流れ

初めてだって怖くない!オーストリアへの入国について

ここはどこ?オーストリアの住所・郵便番号・階の数え方について
-
ウィーン中心部の名チョコ専門店!「Fabienne」(ウィーン市内)

-
【免除申請方法も】オーストリアでの2024年以降のテレビ受信料と支払わな・・・

-
【ウィーン市内最安値かも】圧倒的コスパの「Pizzaria Mafiosi」


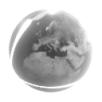




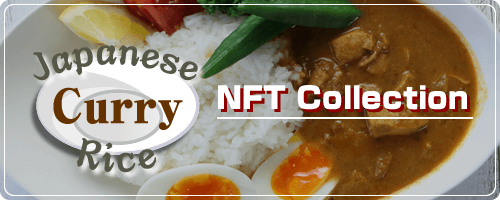




 ちょっと待ってね
ちょっと待ってね